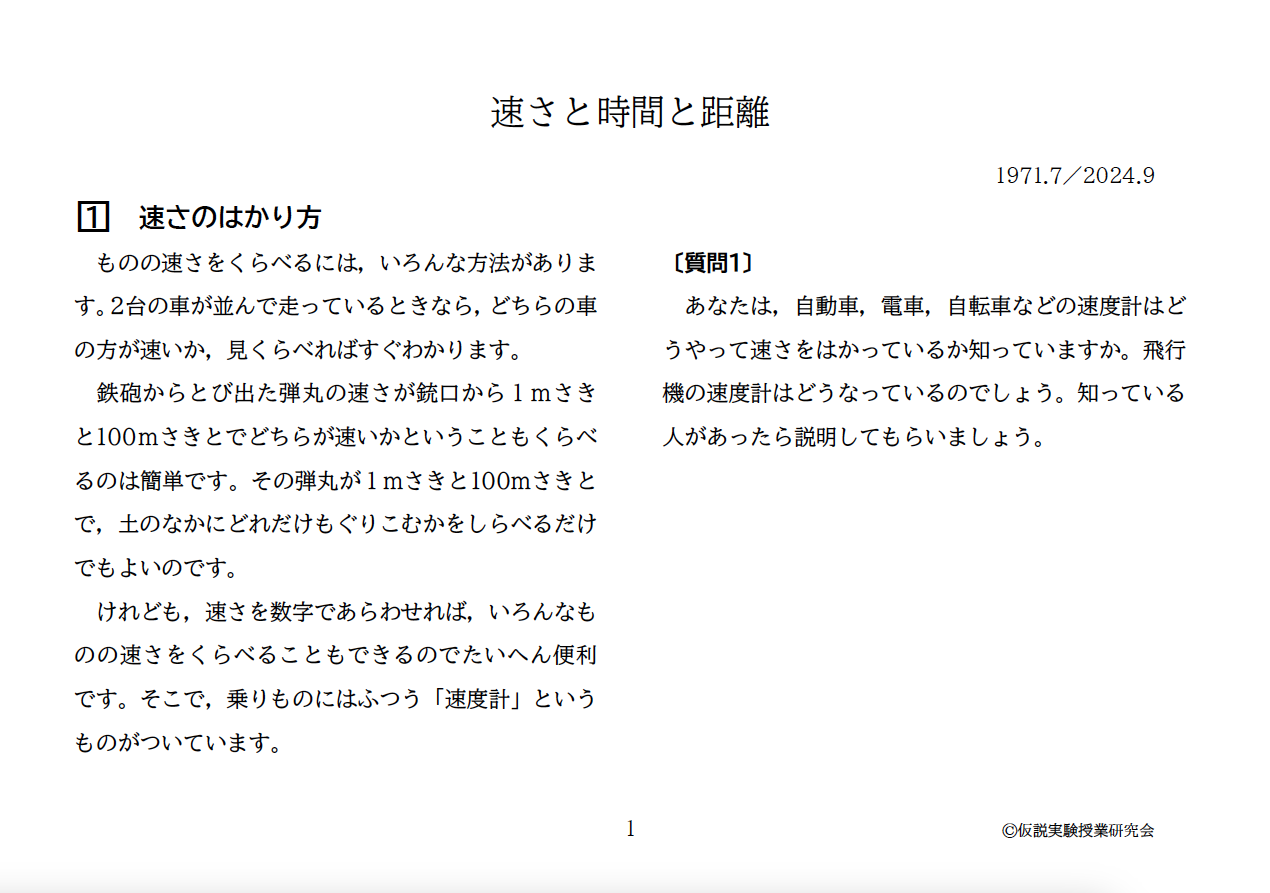【デジタル版授業書】《速さと時間と距離》
*ダウンロードアイテムです。ご注文完了後に画面左の「MYページ」の購入履歴からダウンロードできるようになります。
*このダウンロードデータは,「zip」形式でデータが圧縮され保存されます。ダウンロードした圧縮ファイルを「解凍」してください(ファイルはPDF形式です)。
なお,「解凍」にはパスワードが必要です。ご入金確認後,仮説社からパスワードをお知らせいたします。お急ぎの場合は営業時間内にお電話でお問い合わせください。
仮説実験授業の授業書を,授業支援クラウドサービスを活用してタブレット端末などで授業できるようにしたデジタル版授業書です。授業書は学校の授業で使うことを前提に作られています。実施する際には必ず『仮説実験授業のABC』または 『仮説実験授業をはじめよう』を読み,仮説実験授業の授業運営法にのっとって実施してください。
はじめに
「速さと時間と距離」の問題は,これまでふつうには「わかりきった数学の計算問題」と考えられてきました。(速さ)=(距離)÷(時間)という式を速さの定義式として導入して,あとは計算に習熟させるだけといってもよかったのです。
しかし,この授業書では,(距離)=(速さ)×(時間)を一つの仮説として導入し,実験的にそれをたしかめつつ身につけていくことをねらっています。
(速さ)=(距離)÷(時間) も,
(距離)=(速さ)×(時間) も,
同じことではないかと思われるかもしれませんが,ふつうの定義式で示される〈速さ〉は「平均の速さ」です。しかし,下の式では〈速さ〉をはじめから「瞬間の速さ」として導入できます。〈重さ〉は秤り(重さ計)ではかるように「〈速さ〉は速度計ではかる」として〈瞬間の速さ〉を導入するのが,この授業書の大きな特色といえるでしょう。
小学校高学年から中学・高校の授業に使えます。
◆デジタル版作成にあたって◆
1971年版をもとに,現代に合わせて一部をアップデートしました。
①2ページ
冒頭の文章は「自動車や列車の速度計は,車の回転速度をもとにして」となっていますが,ここでいう「車」とは車輪のことを指しているようです。当時は車輪をたんに「車」と呼んでも違和感を感じなかったのかも知れませんが,現在は「車」といえば一般に「自動車」を指すことが多いです。そこで,「車」が「車輪」を指す場合は「車輪」と置き換えました。
また,その下の「自転車の速度計」についての記述もすこし変更しました。
発電機のことは「ダイナモ」ともいいます。タイヤにダイナモ(発電機)を取り付けて,タイヤの回転で発電して,自転車の前照灯(ライト)を点けています。ゴムタイヤに発電機を接触させて発電する「リムダイ モ」と,タイヤの中心部(車軸)のまわりに取り付ける「ハブダイナモ」 があります。最近の自転車の前照灯は,「ハブダイナモ」か「電池式」がほとんどになっています。
そこで,「自転車の前照燈は,ふつうタイヤにとりつけた小型発電機から電気をとるようになっています」を「自転車の前照燈には,タイヤにとりつけた小型発電機からの電気で点灯するものがあります」という表現に変えました。
②3ページ
飛行機のピトー管の写真を載せました。(村西撮影)
③4ページ
速さを表す単位である「km/h」(キロメートル・パー・アワーと読む)とか「m/秒」(メートル・パー・セカンド(秒)と読む)といった表現がありましたが,「毎時」「毎秒」に統一しました。
④7ページ,11ページ
東海道新幹線は,開業後しばらくは超特急「ひかり号」と特急「こだま号」のみで,「ひかり号」の最高速度は210km/時,東京−新大阪間の停車駅は名古屋と京都のみでした。しかし,現在は「のぞみ号」が最高速度285km/時で走っており,また「のぞみ号」であっても品川駅・新横浜駅に停車するようになっています。
ただ,現在の新幹線の時刻表に差し替えると計算がややこしくなることから,計算がしやすいように,東京−名古屋2時間の「ひかり号」はそのまま残し,「以前は…」といった言葉を添えました。
⑤11ページ,13ページ
グラフの間隔が不正確に描かれていたのを,1分・5秒刻みに直しまし た。
⑥16ページ
〔問題3〕を〔研究問題〕とし,全体を次ページに移しました。問題文に「電車にのったとき,かんたんに速度計がのぞけたら…」となっています。〔問題〕であれば,この「実習」をやらなければならないと誤解される可能性があるので,〔研究問題〕に変更しました。
また,問題文には「5秒ごとか10秒ごとの速さを記録して図のようなグラフを作ってみましょう」と書かれていましたが,グラフは2秒刻みとなっていました。そこで,グラフを差し替えました。
このグラフは京阪鴨東線の出町柳駅から京阪三条駅までの特急電車のデータです(2023年6月,西平龍成計測)。京阪電鉄によると出町柳—京阪三条間の距離は2.3kmです。
⑦全体を通して
「〜してごらんなさい」といった表現は「〜してみましょう」などに変更しました。
それ以外は,1971年版から変更していません。