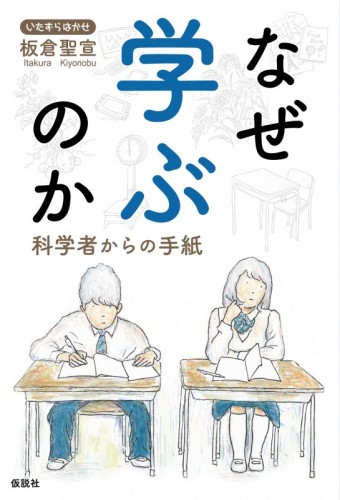なぜ学ぶのか
板倉聖宣 著
「なぜ学ぶのか」「本当に学びがいのある知識とは」「これからの社会をどう生きていけばいいのか」……科学者であり教育者でもある著者から,これからの未来を生きる人たちに贈るメッセージ。★目次★なぜ学ぶのか未来を切り開く力百聞は一見に如かず?死んだらどうなるか予想と討論と実験とたのしく学び続けるために「科学者とあたま」をめぐって寺田寅彦「科学者とあたま」推薦の言葉(小原茂巳)**********「なぜ学ぶのか」……じつは私もよくわからないのです。そりゃあ、一般的にいって「かしこくなるために学ぶのさ」などといえばいいのだったら、私にだっていえます。しかし、「どうしてこんなことを学ばなければならないのか」っていうようなことになると、まるでわからないことが多すぎるのです。それで私は、いつのまにかその「なぜこんなことを学ぶのか」をわかろうとして研究する(学ぶ)ようになってしまいました。おかしな話かもしれません。 もっとも、私にだって、それをなぜ学ぶのかわかることもあります。わかったときはとてもうれしいのです。それで勉強にとても身がはいるようになり、新しい学問の世界がひらけてくるのです。ときたまでもそんなことがあるものだから、やみつきになったというのでしょうか。そんなわけでいつのまにか「なぜ学ぶのか」を研究するのが私の仕事の一つのようにさえなってしまいました。 もちろん、いま中学生であるあなたたちとくらべたら、そりゃあ私の方が知っていることがたくさんあるでしょう。わからないことだらけの私でも、少しはお役に立つこともあるというものです。そこで、私がわかったこと、わからないでいまわかろうとしていることなどを、考え考えお話しすることにしたいと思います。
★★ 詳 細 ★★
頁数:112ページ
サイズ:四六判 並製
初版年月日:2020年6月23日
ISBN:978-4-7735-0302-9
C0037
なぜ学ぶのか 科学者からの手紙
板倉聖宣著 奥まほみ装画
「なぜ学ぶのか」
「本当に学びがいのある知識とは」
「これからの社会をどう生きていけばいいのか」
……科学者であり教育者でもある板倉聖宣さんから,これからの未来を生きる人たちに贈るメッセージ。
★目次★
なぜ学ぶのか
未来を切り開く力
百聞は一見に如かず?
死んだらどうなるか
予想と討論と実験と
たのしく学び続けるために
「科学者とあたま」をめぐって
寺田寅彦「科学者とあたま」
推薦の言葉(小原茂巳)
**********
「なぜ学ぶのか」……じつは私もよくわからないのです。
そりゃあ、一般的にいって「かしこくなるために学ぶのさ」などといえばいいのだったら、私にだっていえます。
しかし、「どうしてこんなことを学ばなければならないのか」っていうようなことになると、まるでわからないことが多すぎるのです。
それで私は、いつのまにかその「なぜこんなことを学ぶのか」をわかろうとして研究する(学ぶ)ようになってしまいました。おかしな話かもしれません。
もっとも、私にだって、それをなぜ学ぶのかわかることもあります。わかったときはとてもうれしいのです。
それで勉強にとても身がはいるようになり、新しい学問の世界がひらけてくるのです。
ときたまでもそんなことがあるものだから、やみつきになったというのでしょうか。
そんなわけでいつのまにか「なぜ学ぶのか」を研究するのが私の仕事の一つのようにさえなってしまいました。
もちろん、いま中学生であるあなたたちとくらべたら、そりゃあ私の方が知っていることがたくさんあるでしょう。
わからないことだらけの私でも、少しはお役に立つこともあるというものです。
そこで、私がわかったこと、わからないでいまわかろうとしていることなどを、考え考えお話しすることにしたいと思います。(第1章「なぜ学ぶのか」より)
第1章「なぜ学ぶのか」全文をnoteで公開しています。